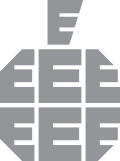七飯のななイイ話 05
大沼の毛皮産業
かつて大沼の産業の一面を担った「大沼養狐場」は、
職人たちの良質な毛皮加工技術として継承されつづける
大正4年(1915)、観光の一面を担ったのが大沼養狐場(おおぬまようこじょう)です。当時、大沼公園を日本全国に宣伝するきっかけとなった一つとしてあげられます。厳しい寒さが訪れる北海道では、動物の皮を衣類や生活の道具として用いる習慣があり、昭和初期までキツネやミンクなどが飼育されてきました。
大沼養狐場は、日魯漁業株式会社が計画し経営したもので、大正7年にカナダから銀黒狐7つがい、ミンク3つがい、フィッチャー3つがいを輸入し、飼育したことがはじまりでした。大正10年(1921)には、この事業を本格化するため、資本金25万円で大沼養狐株式会社(社長松下熊槌)を設立、つねに数十頭のキツネが飼育されていました。大沼湖の西岸字蓴菜沼付近にあった養狐場は、たちまち大沼の名所となり観光客を喜ばせました。また、衛生面においても配慮されていたといいます。
養狐事業は、昭和15年頃まで続きましたが、戦争の影響もあって会社が解散。その後、昭和20年(1945)に北海道大沼にある鍋谷毛皮店(鍋谷千代蔵)によって、ミンクの飼育と毛皮加工がはじめられ、戦時中は一時中断されたものの戦後は序々に再開されました。
農林省の推定によると、昭和28年(1953)アメリカから輸入された種畜はわずか数十頭であったのに対し、その後日本で飼われたミンクは、昭和29年に1千頭、昭和34年には3万5先頭、昭和38年25万頭、昭和40年40万頭に達し、そのうち20万頭を毛皮にして国内外へ送り出したという記録があります。
当時、「宝石を生む動物」というキャッチフレーズですすめられたこのミンク養殖は、その95%が北海道で行われていました。寒冷な気候がミンク毛の生育に適していること、ミンク飼料の鯨肉や魚肉が安く手近に入ることが、発展の理由にあげられます。


現在でも、毛皮のナメシから縫製・仕上げを一貫し製造している若松毛皮では、海外での需要も 多く、物産展やクラフトフェア、オーダーメイドにも対応しています。かつてより職人の数は減少したものの、世界に誇る良質な毛皮を加工する技術は現在も継承されつづけています。

取材協力 / 有限会社 若松毛皮